今やスマートフォンやパソコンを使うには欠かせないWi-Fi(ワイファイ)。そのWi-Fiには「2.4GHz帯(たい)」と「5GHz帯(たい)」という2つの電波があることをご存じですか?
この2つには「電波の届きやすさ」や「速度」に違いがあり、場面に応じて使い分けることで、より快適なインターネット環境をつくることができます。
本記事では、Wi-Fiの「2.4GHz帯」と「5GHz帯」の違いや、それぞれの使い方について、イラストを使いながらわかりやすく解説します。

「帯(たい)」は、電波の周波数帯域(周波数の範囲)のことです。
たとえば2.4GHz帯は、2.4GHzぴったりの周波数だけでなく、その前後を含む幅のある範囲全体を指します。
なぜWi-Fiルーターから2つの電波が出ているのか?

もともとは「2.4GHz帯」だけだった
家庭用Wi-Fiが普及し始めた当初は、2.4GHz帯の電波だけが使われていました。
この2.4GHz帯は、電子レンジやコードレス電話、Bluetoothなど身近な家電でも昔から利用されている帯域で、壁や床を通りやすく扱いやすいという特長があり、そのためWi-Fiにも採用されました。

Wi-Fiが普及し始めたのは西暦2000年ごろで、当初は2.4GHz帯の電波だけでした
解決策として登場した「5GHz帯」
しかし、Wi-Fiの利用者が増え、家中の機器が2.4GHz帯に集中することで、
「電波が混雑してつながりにくい」
「電子レンジを使うとWi-Fiが切れる」
「通信速度が遅くなる」
といったトラブルが起こるようになりました。
こうした問題を解消するために登場したのが、5GHz帯のWi-Fiです。 5GHz帯は2.4GHz帯に比べて利用者が少なく、電波干渉が起きにくいため、通信が安定しやすく速度も速いという大きなメリットがあります。
現在では、ほとんどのWi-Fiルーターが2.4GHz帯と5GHz帯の両方に対応しており、自宅の環境や接続する機器に応じて使い分けられるようになっています。
Wi-Fiルーターが2つの電波を出しているのは、
- 「壁や床を通りやすく扱いやすい電波(2.4GHz帯)」
- 「通信が安定しやすく速度も速い電波(5GHz帯)」
を、選ぶことでより快適な通信にするためです。

今のWi-Fiは、複数の電波を同時に使うのが基本となっています
最近では「6GHz帯」も登場
さらに2022年に登場したWi-Fi 6Eでは、「6GHz帯」というもっと高速な電波も使えるようになりました。
これにより、従来の2.4GHz帯や5GHz帯に比べて電波干渉が少なく、より高速な通信が可能になります
特に、多くの機器が同時に接続されるスマートホーム環境や、高速な通信が求められるオンラインゲーム、4K・8Kなどの動画視聴でその真価を発揮します。

ただし、「6GHz帯」で通信するには、スマホやパソコンなどの端末側も、6GHz帯に対応している必要があります
ざっくりまとめ
| 項目 | 2.4GHz帯 | 5GHz帯 | 6GHz帯 (Wi-Fi 6E~) |
|---|---|---|---|
| 特徴 | 昔から使われている Wi-Fi の電波 | 比較的新しく、スピードが速い | 最新の電波で、より快適 |
| 通信速度 | やや遅め | 速い | とても速い |
| 距離・障害物 | 遠くまで届きやすく、壁や床にも強い | 近くなら快適だが、壁や障害物に弱い | 障害物に弱く、届く範囲はややせまい |
| 他の電波との干渉 | 家電などと電波が重なりやすい | 2.4GHzよりは干渉が少ない | まだ使っている人が少なく、とてもすいている |
| 向いている使い方 | 玄関やお風呂場など、ルーターから離れた場所での使用 | リビングや書斎など、ルーターの近くで動画視聴やリモートワーク | 対応機器がある場合や、動画視聴・ゲームをより快適に楽しみたいとき |
2.4GHz帯と5GHz帯の違いとは

通信速度が違う
- 2.4GHz帯:遅い
- 5GHz帯:速い
2.4GHz帯の電波は、帯域(データの通る道)が狭く、一度に送れるデータの量が限られているので、通信速度はそれほど速くありません。
さらに、電子レンジやコードレス電話などの家電製品でも使われている周波数なので、電波が混み合いやすく、その影響によって遅くなることもあります。

2.4GHz帯はデータの通り道が狭いです
それに対して、5GHz帯の電波は帯域が広いので一度に多くのデータを送れます。このため2.4GHz帯に比べて通信速度が速いです。
また、5GHz帯は他の家電製品でもあまり使われていません。このため電波の混雑が少なく、より安定して高速な通信ができます。

5GHz帯は2.4GHz帯よりも、同じ時間にたくさんのデータを送受信できるので、その分スピードが速くなります
「GHz(ギガヘルツ)」ってなに?
GHz(ギガヘルツ)は、電波や音などの「波」が1秒間に何回繰り返されるかを表す周波数の単位です。
1Hz(ヘルツ)は、波が「1秒間に1回」繰り返すことを意味するので、例えば1GHz(ギガヘルツ)なら、その10億倍、つまり1秒間に10億回も波が繰り返されることになります。

繰り返される波の数が多いほど「高周波」と言い、少ないほど「低周波」と言われます

電波の届きやすさが違う
- 2.4GHz帯:遠くまで届く(壁やドアなどにも強い)
- 5GHz帯:距離は短い(壁やドアに弱い)
2.4GHz帯は波長が長いため、家の中の壁や家具をすり抜けやすく、2階や離れた部屋まで届きやすいです。
また、5GHz帯は波長が短く、障害物に弱いため届く範囲は狭いですが、そのぶん近距離では非常に快適な通信が可能です。

Wi-Fiルーターと同じ部屋の中なら、5GHzを使いましょう
道路で言うと、2.4GHz帯は「一般道」、5GHz帯は「高速道路」に例えることができます

2.4GHz帯と5GHz帯の違いとは?
- 2.4GHz帯は通信速度は控えめだが、壁や障害物に強く、広範囲に電波が届きやすい
- 5GHz帯は障害物に弱く遠くまで届かないが、通信速度が速く安定した高速通信が可能
2.4GHz帯の特徴

2.4GHz帯は、電波が遠くまで届きやすく、広い範囲にわたってつながりやすいのが特徴です。
ルーターから離れた部屋や、少し離れた場所でもWi-Fiが届きやすく、古いスマートフォンや家電なども接続することができます。
2.4GHz帯のメリット
- 遠くまで飛びやすい
たとえば、1階にあるルーターの電波が2階の部屋まで届きます。
- 障害物に強い
壁や家具などで部屋が分かれていても、5GHz帯に比べてつながりやすいです。
- 対応する機器が多い
古いスマートフォンやプリンター、IoT家電(エアコン、ロボット掃除機など)も接続可能です。
2.4GHzのデメリット
- 通信速度が遅くなりやすい
そもそも5GHz帯に比べて通信速度が遅く、電波も混雑しやすいため速度は遅くなりやすいです。
- 他の家電と電波がぶつかる
電子レンジやBluetooth機器も2.4GHz帯を使っているため、電波干渉が起きやすいです。
ざっくりまとめ
- 電波の到達距離が長く、壁や家具があっても比較的届きやすい
- 古い機器や家電も対応していることが多い
- 電波の混雑が起こりやすく速度が遅くなる場合がある
5GHz帯の特徴

5GHz帯は、通信速度が速く、大きなデータもスムーズにやりとりできます。
たとえば、高画質の動画を見たり、オンラインでゲームをしたりする時にも、ストレスなく快適に使えます。
また、電子レンジやBluetoothといった家電の電波とぶつかりにくいので、通信が安定しやすいです。
5GHz帯のメリット
- 高速通信が可能
高い周波数帯を使うので、短時間でより多くのデータを送受信できます。動画視聴や大きなファイルのダウンロードに向いています。
- 複数機器の同時接続でも安定
帯域(データが通る道の幅)が広く、複数台が同時に通信しても速度低下しにくいです。
- 電波干渉が起きにくい
2.4GHz帯に比べると、5GHz帯は使っている人や機器が少ないため混雑しにくく、電波のぶつかり(干渉)が起きにくい特徴があります。
さらに、5GHz帯は使えるチャンネル数が多いので、近くのWi-Fi同士でも別のチャンネルを使うことができ、電波干渉が起きにくくなっています。
チャンネル数ってなに?
Wi-Fiのチャンネル数とは、テレビで言う「NHK」や「日本テレビ」のようなチャンネルと同じ意味です。
テレビのチャンネルが多いといろんな番組を楽しめるように、Wi-Fiもチャンネルが多いと、複数の経路からネットにつなぐことができて、より快適に使うことができます。

チャンネルが複数あることで干渉が減り、通信を安定させることができます
5GHz帯のデメリット
- 壁や床に弱い
5GHz帯は周波数が高いため、壁や床などの障害物を通り抜けにくく、部屋が変わると電波が届きにくくなることがあります。
- 通信範囲が狭い
2.4GHz帯に比べて電波が届く距離が短く、家全体をカバーするにはメッシュWi-Fi化などの工夫が必要になる場合があります。
- DFSに注意が必要
5GHz帯は電波干渉に強いですが、「DFS」という仕組みによって一時的に通信が止まったり、別のチャンネルに切り替えられる可能性があります。
DFSとは
Dynamic Frequency Selection(ダイナミック・フリークエンシー・セレクション/動的周波数選択)の略で、レーダーや気象観測システムなどの重要な無線設備と干渉しないように、Wi-Fiの周波数を自動で切り替える仕組みです。
実は5GHz帯は、気象レーダーや航空機のレーダーにも使われています。
このため、電波法に基づく技術基準によってDFSの搭載が義務付けられていて、重要な電波との干渉を防ぐようになっているのです。

ただし、空港周辺や海沿い、山間部などの、レーダー施設付近以外であれば心配することはありませんし、5GHz帯のチャンネルをW52帯(36/40/44/48ch)にすれば回避することもできます
5GHz帯は古いスマホやパソコンなどでは利用できない場合があります。
これは、昔つくられた機器が5GHz帯に対応していないからです。
当時は主に2.4GHz帯しか使われていなかったので、古い機器には5GHzの電波を受け取るしくみが入っていないのです。

対応機器が少ないのはデメリットですが、逆に言えば、接続する人も少ないので、混雑しにくいというメリットでもあります。
ざっくりまとめ
- 高速通信が可能で動画視聴やオンラインゲームに向いている
- 電波干渉が少なく、複数つないでも安定した通信ができる
- 障害物に弱く、距離が離れると届きにくい
2.4GHz帯と5GHz帯、どっちを使えばいいの?

2.4GHz帯と5GHz帯は、どちらもメリットデメリットがあって、どっちを使えばいいのか迷いますよね。 この2つは、それぞれ次のような使い方がおすすめです。
こんな時は2.4GHz帯
- Wi-Fiルーターから離れた場所で使うとき
2.4GHz帯は電波が遠くまで届きやすいため、部屋をまたいだり、階をまたいで使う場合に適しています。
- 壁や家具など障害物が多い場所
壁や棚があるような場所でも、2.4GHz帯は電波が通りやすく、安定してつながります。
- 古いスマホ・家電をつなげるとき
古いスマホやゲーム機・家電などは、ほぼ2.4GHz帯を使って通信します。
こんな時は5GHz帯
- Wi-Fiルーターと同じ部屋にいるとき
同じ部屋であれば壁などの障害物が少ないため、5GHz帯の高速かつ安定した通信というメリットを活かせます。
- 高画質の動画視聴やオンラインゲームなどをするとき
通信が速くて安定しているので、4K動画やゲームなど、大きなデータを使うときに適しています。
- 通信速度が遅いと感じたとき
2.4GHz帯は電子レンジなどの家電と電波がかぶって混雑しやすいので、5GHz帯に切り替えると速度が改善することがあります。
迷ったら、まず5GHz帯でつないでみる
2.4GHz帯と5GHz帯で迷ったら、まずは5GHz帯で接続してみましょう。
通信速度が速い5GHz帯でつないでみて、もし通信が不安定な場合であれば2.4GHz帯に切り替える、というやり方がおすすめです。

5GHz帯は、スマホやパソコンなどの「通信速度を重視する機器」に適した周波数帯です。
ざっくりまとめ
- ルーターから離れた場所や壁の多い場所では、2.4GHz帯が適している
- ルーターと近い距離で高速通信を求めるなら、5GHz帯がおすすめ
- 迷ったらまずは5GHz帯で接続する
2.4GHz帯と5GHz帯、見分け方と切り替え方

2.4GHz帯と5GHz帯の違いは分かったけど、「2つの見分け方は?」「切り替えるには?」と思う方も多いはず。
ここでは、2.4GHz帯と5GHz帯の見分け方や切り替え方について解説します。
見分け方は「SSID」を確認すればOK

2.4GHz帯と5GHz帯を見分けるには、Wi-FiルーターのSSID(Wi-Fiの名前)を確認します。

SSIDは、スマホやパソコンのWi-Fi設定画面で見ることができます
Wi-Fiの設定画面で表示されるSSIDには、電波を区別するために「2G」や「5G」と付いていることが多く、SSIDに「2G」が含まれているものは「2.4GHz帯」、「5G」が含まれているものは「5GHz帯」を表しています。
ただし、区別のしかたはメーカーによって異なる

ただし、メーカーによっては、SSIDが「2G」や「5G」ではなく「G」や「A」と表示されることがあります。
これは、初期のWi-Fiが「IEEE 802.11g」や「IEEE 802.11a」と言った規格名で呼ばれていた時の名残です。

Wi-Fiが使われ始めた頃のSSIDは、規格名の最後に付いているアルファベットを使って区別していました
現在のWi-Fiは、「Wi-Fi 4」「Wi-Fi 5」「Wi-Fi 6」といった世代番号で呼ばれるようになり、それに伴い、SSIDも「2G」や「5G」と表記されることが多くなりましたが、一部では今も「G」や「A」を使っているため、SSID名はメーカーによって異なります。
2.4GHz帯と5GHz帯以外にもう一つ?3つめの共通SSIDって?
![区別の仕方が表示されないSSIDは「共通SSID]ということを表したイラスト](https://yasashiiwi-fi.com/wp-content/uploads/2025/08/k10_11.png)
また最近のWi-Fiルーターには、2.4GHz帯と5GHz帯の他に、SSIDの末尾に何もついていないSSID名が表示されることがあります。
このSSIDは「共通SSID」と呼ばれ、2.4GHz帯と5GHz帯を一つにまとめたSSIDで、Wi-Fiルーターが「バンドステアリング(周波数帯を自動で切り替えてくれる機能)」に対応している場合に表示されます。
この場合、Wi-Fiの設定画面には
- 2.4GHz帯のSSID
- 5GHz帯のSSID
- 共通SSID(2.4GHz帯と5GHz帯の2つが一つにまとめられたSSID)
の3つが表示されることになります。
バンドステアリングとは、Wi-Fiルーターが「2.4GHz帯」と「5GHz帯」のどちらの周波数帯を使うかを、Wi-Fiルーターが自動で判断して切り替えてくれる機能です。
この機能を使う場合は、「共通SSID」と呼ばれる、区別表示の無いSSIDを選びます。

たとえば、ルーターから離れた場所では「電波が届きやすい2.4GHz帯」に、ルーターの近くでは「通信速度が速い5GHz帯」に、自動で切り替わるようになります
ざっくりまとめ
- SSIDを確認することで見分けることができる
- ただしメーカーによって表記に違いがある
- バンドステアリング機能があるWi-Fiルーターの場合、SSIDは3つ表示される
切り替え方はSSIDを選びなおすだけ

2.4GHz帯と5GHz帯を切り替えたいときは、接続したいSSIDを選び直すだけでOKです。
スマホやパソコンのWi-Fi設定画面に表示されるSSIDの中から、2.4GHz帯用または5GHz帯用の名前を選択すれば、すぐに切り替えることができます。
上手く切り替えればもっと快適に
Wi-Fiは、一度接続すると次回からは自動的につながる仕組みになっています。そのため、普段は特に切り替えをせずに同じSSIDを使い続けている方も多いでしょう。
しかし、利用する場所に合わせて「2.4GHz帯」と「5GHz帯」を使い分けると、通信がより安定したり、速度が向上する場合がありますので、場所に応じて上手に使い分けましょう。

意図的に使い分けるのか…
また、バンドステアリング機能のあるWi-Fiルーターでも、環境や端末によっては自動切り替えがうまく働かない場合がありますので、Wi-Fiは必要に応じて「手動で切り替えられる」点を覚えておくと便利です。
バンドステアリング機能があるWi-Fiルーターで手動切り替えをする場合は、バンドステアリング機能をOFFにする必要があります。
2.4GHz帯と5GHz帯、両方活かせるルーターの選び方

せっかく2.4GHz帯と5GHz帯の違いを理解しても、古いルーターではそのメリットを体感できません。
ここでは、2つの周波数をしっかり使い分けられる、ルーター選び方のポイントを解説します。
Wi-Fi 6以降に対応しているか確認する
現在よく使われているWi-Fiは、いくつかの世代(規格)に分かれています。

例えばWi-Fi 6なら、第6世代のWi-Fiという意味です
| 正式名称 | 通称(世代名) | 登場年 | 周波数帯 |
|---|---|---|---|
| IEEE 802.11 | – | 1997年 | 2.4GHz |
| IEEE 802.11a | – | 1999年 | 5GHz |
| IEEE 802.11b | – | 1999年 | 2.4GHz |
| IEEE 802.11g | – | 2003年 | 2.4GHz |
| IEEE 802.11n | Wi-Fi 4 | 2009年 | 2.4GHz / 5GHz |
| IEEE 802.11ac | Wi-Fi 5 | 2013年 | 5GHz |
| IEEE 802.11ax | Wi-Fi 6 | 2019年 | 2.4GHz / 5GHz |
| IEEE 802.11ax (6GHz対応) | Wi-Fi 6E | 2021年 | 2.4GHz / 5GHz / 6GHz |
| IEEE 802.11be | Wi-Fi 7 | 2024年(予定) | 2.4GHz / 5GHz / 6GHz |
新しい規格ほど通信速度や安定性が向上していて、中でもWi-Fi 6以降の規格は、複数の端末を同時に快適に使えるよう設計されており、より多くの機器を接続する現代の環境に適しています。
これからルーターを購入する場合や買い替えを検討している場合は、Wi-Fi 6以上(Wi-Fi 6EやWi-Fi 7など)に対応したモデルがおすすめです。

Wi-Fi 6以降のWi-Fi規格は、通信のセキュリティもより強くなっていて安心です
アンテナの数や性能にも注目する
ルーターに搭載されているアンテナの数や性能によって、Wi-Fiの電波の強さや安定性は大きく変わります。

家族が3〜4人いる家庭では、スマホやパソコン、ゲーム機、スマート家電など、Wi-Fiに接続する機器が意外と多くなりがちです
こうした複数の端末が同時に通信する環境では、アンテナの本数が多いものや、ビームフォーミング、MU-MIMO(同時通信機能)などの性能が高いルーターを選ぶことで、より快適にインターネットを利用できます。
「ビームフォーミング」や「MU-MIMO」は、電波を効率よく複数の機器に届けるための新しい技術です。これらの機能があると、通信が混み合っても安定しやすくなります。
バンドステアリング対応がおすすめ
バンドステアリングとは、2.4GHz帯と5GHz帯の電波を1つのSSIDにまとめて、自動的に最適な周波数に切り替えてくれる機能です。
これがあると、自分で周波数を選ぶ必要がなく、その場にあった周波数での接続が可能になります。
新しいルーターではほとんど対応していますが、購入前に「バンドステアリング」や「スマートコネクト」という機能名をチェックしましょう。

バンドステアリングは、メーカーによっては、「スマートコネクト」と呼ばれることもあります
Wi-Fiルーターを選ぶ際は、接続可能台数が10〜20台に対応しているモデルがおすすめです。
また、メッシュWi-Fiに対応したルーターであれば、家のすみずみまで電波が届きやすくなり、より安定したWi-Fi接続が可能になります。
ざっくりまとめ
- 2.4GHz帯と5GHz帯のメリットを両方活かすには、新しいルーターへの買い替えがおすすめ
- アンテナの数やバンドステアリング機能などの性能にも注目する
- Wi-Fi6以降に対応したWi-Fiルーターなら、セキュリティもより安心
おすすめのWi-Fiルーターは
ここでは、日本製のおすすめルーターを紹介します。
2.4GHz帯と5GHz帯の性能を最大限に活かすためには、それに対応したルーターを選ぶことが欠かせません。
なかでも日本製のルーターは、操作がわかりやすく、サポート体制も充実しているため、初めての方でも安心して使えます。
今回は、そんな安心感のある国内メーカーのモデルを厳選してご紹介します。

全て「Wi-Fi6」で、「バンドステアリング」「メッシュWi-Fi」に対応したモデルです
| メーカー | モデル名 | 最大速度(5GHz帯) | アンテナ数 | 特徴・おすすめポイント |
|---|---|---|---|---|
| バッファロー | WSR-3200AX4S | 2402 Mbps | 4本 | コスパ良し、4本アンテナで広範囲カバー。初心者向け。 |
| NEC | PA-WX6000HP | 4803 Mbps | 8本 | ハイエンドモデル。高速&安定、MU-MIMO対応。ビジネスや大家族向け。 |
| ELECOM | WRC-X5400GS | 4803 Mbps | 4本 | コスパ良し、省エネ設計。シンプルで初心者にも使いやすい。 |
バッファロー WSR-3200AX4S
バッファローのWSR-3200AX4Sは、4本のアンテナで広範囲をカバーし、Wi-Fi 6対応で最大2402Mbpsの高速通信が可能です。バンドステアリングやメッシュWi-Fiにも対応しており、家中どこでも安定した接続ができます。初心者にも扱いやすい設定画面と手厚いサポートが魅力です。
NEC PA-WX6000HP
NECのPA-WX6000HPは、8本のアンテナを搭載し、Wi-Fi 6で最大4803Mbpsの高速通信を実現。バンドステアリングとメッシュWi-Fi対応で、多数の端末を快適に接続可能です。安定性と高性能を求めるビジネスユーザーや大家族に最適なハイエンドモデルです。
ELECOM WRC-X5400GS
ELECOMのWRC-X5400GSは、4本のアンテナを備えたWi-Fi 6対応ルーターで、最大4803Mbpsの高速通信に対応。バンドステアリングとメッシュWi-Fi機能を搭載し、省エネ設計で初心者でも簡単に使えます。コストパフォーマンスの高いシンプルなモデルとしておすすめです。
まとめ
2.4GHz帯と5GHz帯にはそれぞれ長所と短所があり、使う場所や利用の仕方によって向いている電波は違います。
たとえば、広い範囲に電波を届けたいときは2.4GHz帯、速度を重視したいときは5GHz帯といった具合です。
また、最近のルーターには状況に応じて自動的に2.4GHz帯と5GHz帯を切り替える機能も備わっているため、難しい設定をしなくても快適に使えるようになっています。
違いを理解して上手に使い分けることで、日常のWi-Fi環境はぐっと快適になります。
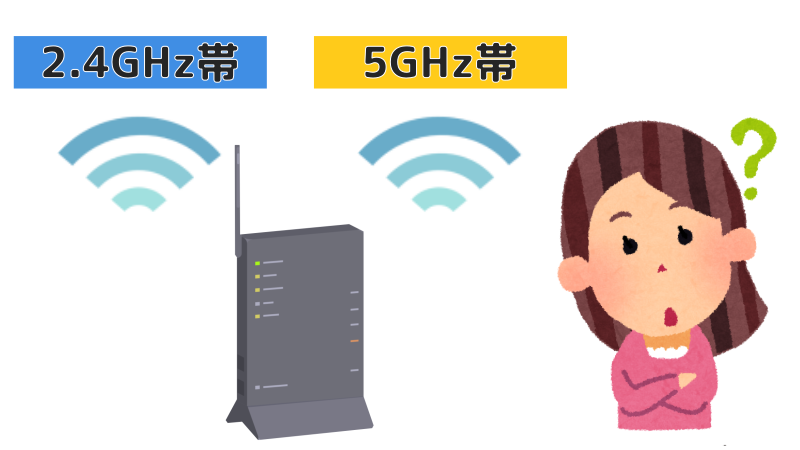

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4bc6e433.53903eb7.4bc6e434.aabe81e1/?me_id=1432996&item_id=10005129&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsootune%2Fcabinet%2Fonesell091%2Fhino3f1679e716_0.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4bc6e703.f7870615.4bc6e704.bb5d80de/?me_id=1428581&item_id=10000489&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshop-24%2Fcabinet%2Fcompass1734962458.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4bc6e006.0920c01a.4bc6e007.52c2aef7/?me_id=1395626&item_id=10004508&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fakibasoko%2Fcabinet%2Fimgrc0101229677.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

